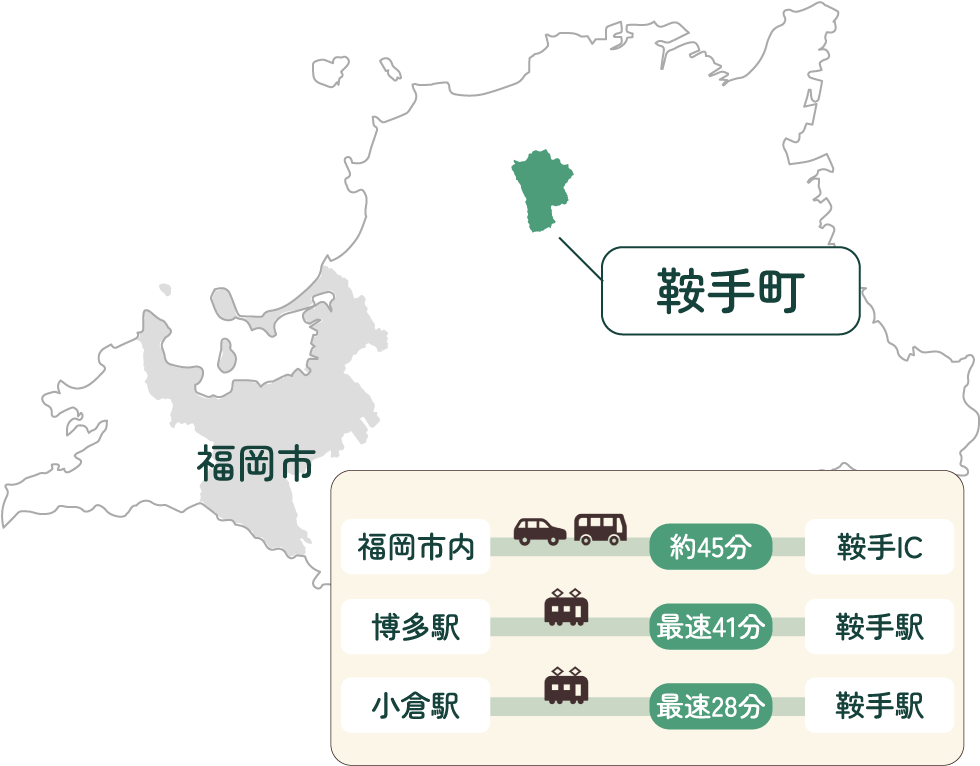定期予防接種のご案内(乳幼児・児童)
ここから本文です。
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした、病気に対する抵抗力(免疫)は生後3か月から8か月までに自然に失われていきます。この時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要が出てきます。これに役立つのが予防接種です。
こどもの発育と共に外出の機会が多くなります。保育園や幼稚園に入るまでには予防接種で免疫をつけ、感染症にかからないように予防しましょう。
乳幼児・児童に実施する定期予防接種には、次の種類があります。
かかりつけの医療機関で接種します。かかりつけの医療機関が予防接種県内広域指定医療機関であるかどうか、病院で直接お尋ねください。指定医療機関以外で接種する場合は、依頼書が必要です。不明な場合や依頼書が必要な際は、所属までご連絡ください。
五種混合(令和6年4月から定期接種となりました)
ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ(急性灰白髄炎)、Hib(ヒブ感染症)の予防ワクチンです
対象年齢
生後2か月~90か月未満(標準的接種年齢:1期初回・・・生後2か月~12か月未満、1期追加・・・1期初回終了後12か月~18か月)
個人通知
生後2か月時に問診票を送付しています
接種回数(間隔)
- 1期初回・・・3回(21~56日間隔)
- 1期追加・・・1回(初回接種後6か月以上の間隔)
(注意)五種混合ワクチンを接種した場合、四種混合ワクチンとHib(ヒブ感染症)ワクチンの接種は必要ありません。
四種混合
ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ(急性灰白髄炎)の予防ワクチンです
対象年齢
生後2か月~90か月未満(標準的接種年齢:1期初回・・・生後2か月~12か月、1期追加・・・1期初回接種後12か月~18か月)
接種回数(間隔)
- 1期初回・・・3回(21~56日間隔)
- 1期追加・・・1回(初回接種後6か月以上の間隔)
(注意)五種混合ワクチンを接種した場合、四種混合ワクチンとHib(ヒブ感染症)ワクチンの接種は必要ありません。
Hib(ヒブ感染症)
インフルエンザB型による感染症の予防ワクチンです
対象年齢
生後2か月~60か月未満(標準的接種年齢:初回・・・生後2か月~7か月未満、追加・・・初回接種後7か月~13か月)
接種回数(間隔)
接種開始時期により回数が異なります
初回接種を生後2か月~7か月に開始
- 初回3回(27日以上の間隔で生後12か月までに)
- 追加1回(初回終了後7か月以上の間隔)
(注意)ただし生後12か月までに3回の初回接種を終了せずに追加接種を行う場合は、初回接種後27日以上の間隔で1回
初回接種を生後7か月~12か月に開始
- 初回2回(27日以上の間隔で生後12か月までに)
- 追加1回(初回終了後7か月以上の間隔)
(注意)ただし生後12か月までに2回の初回接種を終了せずに追加接種を行う場合は、初回接種後27日以上の間隔で1回
初回接種を生後12か月以降に開始
初回1回
小児用肺炎球菌
肺炎球菌(20価)による感染症の予防ワクチンです
令和6年10月から沈降型20価肺炎球菌結合型ワクチンが追加となりました。
対象年齢
生後2か月~60か月未満(標準的接種年齢:初回・・・生後2か月~7か月、追加・・・生後12か月~15か月未満で初回接種終了後から60日以上の間隔)
個人通知
生後2か月時に問診票を送付しています
接種回数(間隔)
接種開始時期により回数が異なります
初回接種を生後2か月~7か月に開始
- 初回3回(27日以上の間隔で生後24か月までに)
- 追加1回(初回終了後60日以上の間隔で生後12か月以降に)
(注意)ただし2回目の接種が生後12か月を超えた場合、3回目の接種は行わない
初回接種を生後7か月~12か月に開始
- 初回2回(27日以上の間隔で生後24か月までに)
- 追加1回(初回終了後7か月以上の間隔)
初回接種を生後12か月~24か月に開始
初回2回(60日以上の間隔)
初回接種を24か月以降に開始
初回1回
BCG
結核菌感染症の予防ワクチンです
対象年齢
生後12か月未満(標準的接種年齢:生後5か月~8か月)
個人通知
生後2か月時に問診票を送付しています
接種回数(間隔)
1回(他の生ワクチン予防接種(MR、水痘、麻しん、風しん、おたふくかぜ)との間隔は27日以上あけましょう)
麻しん風しん混合(MR)/麻しん単独ワクチン・風しん単独ワクチン
麻しん(はしか)及び風しんの予防ワクチンです
対象年齢
- 1期・・・生後12か月~24か月未満
- 2期・・・5歳以上7歳未満の者で小学校就学1年前~小学校就学日の前日まで(幼稚園・保育園の年長児)
個人通知
1期は生後2か月時に問診票を送付しています。2期は年長時に通知しています
接種回数(間隔)
- 1期・・・1回
- 2期・・・1回(他の生ワクチン予防接種(BCG、水痘、おたふくかぜ)との間隔は27日以上あけましょう)
麻しんまたは風しんにかかった人は、かかってない方の単独ワクチンを接種することもできます。かかりつけ医にご相談ください。
水痘
水痘(みずぼうそう)の予防ワクチンです
対象年齢
生後12か月から36か月未満(標準接種年齢:初回・・・生後12か月~15か月、追加・・・初回接種後6か月~12か月)
個人通知
生後2か月時に問診票を送付しています
接種回数(間隔)
- 初回・・・1回
- 追加・・・1回(初回接種後3か月以上の間隔)
(注意)他の生ワクチン予防接種(BCG、MR、麻しん、風しん、おたふくかぜ)との間隔は27日以上あけましょう。また、すでに水痘にかかった人は対象外です
日本脳炎
対象年齢
- 1期・・・生後6か月~90か月未満
- 2期・・・9~12歳(標準的接種年齢:1期初回・・・3歳、1期追加・・・4歳、2期・・・9歳(小学校4年生))
個人通知
1期は生後2か月時に問診票を送付しています。2期は、小学校4年生時に個人通知しています
接種回数(間隔)
- 1期初回・・・2回(6~28日間隔)
- 1期追加・・・1回(初回接種後6か月以上の間隔)
平成7年4月2日~平成19年4月1日に生まれた人は、20歳未満の間に接種していない回数分を接種することができます。接種回数や間隔については、かかりつけ医にご相談ください
二種混合
対象年齢
11~12歳(標準的接種年齢:12歳(小学校6年生))
個人通知
小学校5年生3月頃に個人通知しています
接種回数(間隔)
1回(他の予防接種との間隔は6日以上あけましょう)
子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス・HPV)
発がん性HPV(ヒトパピローマウイルス)感染による子宮頸がんの予防ワクチンです
対象年齢
12歳となる日の属する年度初日から16歳となる日の属する年度末日までの間にある女子(小学校6年生~高校1年生)(標準的接種年齢:中学校1年生)
個人通知
小学校6年生女子に4月頃、個人通知しています
接種回数(間隔)
ワクチンの種類により接種間隔が異なります
- 2価ワクチン・・・3回(1か月以上の間隔で2回接種後、1回目の接種から5か月以上かつ2回目から2か月半以上の間隔で1回)
- 4価ワクチン・・・3回(2か月以上の間隔で2回接種後、3か月以上の間隔で1回)
- 9価ワクチン・・・3回(2か月以上の間隔で2回接種後、1回目の接種から6か月の間隔で1回)
平成9年4月2日~高校2年生学年齢に生まれた人のうちキャッチアップ接種期間中に接種し、接種が完了していない人は令和8年3月31日まで接種していない回数分を接種することができます。詳細は最新情報をご確認ください。
B型肝炎
B型肝炎(HBV)予防のワクチンです
対象年齢
生後12か月未満(標準的接種年齢:生後2カ月、3カ月、7~8カ月)
個人通知
生後2カ月時に問診票を送付しています
接種回数
3回(27日以上の間隔をおいて2回、さらに初回接種後140日以上を経過した後に1回)
(注意)HBs抗原陽性の妊婦から生まれた乳児として、健康保険の給付によりB型肝炎ワクチンの投与の一部または全部を受けた方は定期接種の対象外となります
ロタウイルス
ロタウイルス感染症予防のワクチンです。ワクチンの種類により、対象年齢や回数が違います。
対象年齢
- ロタリックス:6週~24週
- ロタテック:6週~32週(標準的接種年齢:初回接種は、生後2か月から15週未満)
個人通知
生後2カ月時に問診票を送付しています
接種回数(間隔)
- ロタリックス:2回(27日以上の間隔)
- ロタテック:3回(27日以上の間隔)
お問い合わせ
所属課局:健康こども課健康増進係
電話番号:0949-42-2117