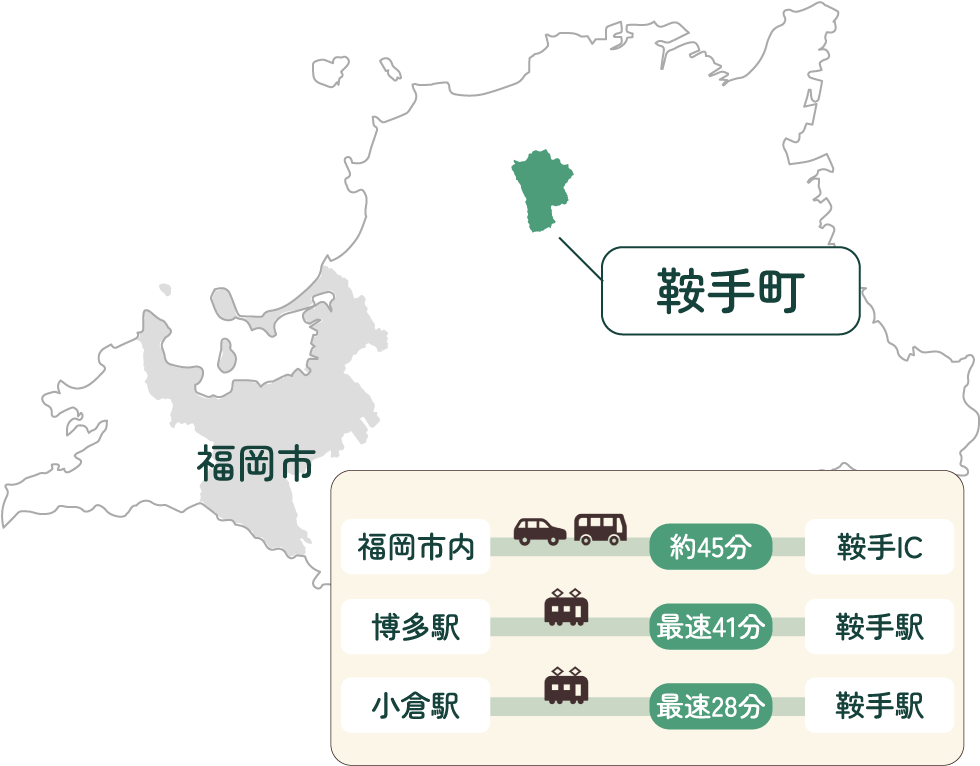固定資産税
ここから本文です。
|
|
| 耐震改修をした既存住宅に対する税の減額 | バリアフリー改修住宅に対する固定資産税減額制度 | 省エネ改修住宅に対する固定資産税減額制度 |
| 償却資産に対する課税 | 縦覧・閲覧制度 |
| 土地・建物の相続登記 | 住宅用家屋証明の申請 |
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者ですが、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、現に所有している人が納税義務者となります。
| 土地 |
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
課税の仕組み
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4%)
土地に対する課税
固定資産評価基準に基づいて、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目(登記上の地目ではありません。)によります。また、地積については原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
居住用の宅地
- 居住用に供される宅地(住宅の床面積の10倍までの用地)には、下記のような特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。この部分については、価格の6分の1の額を課税標準額とします。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。この部分の価格の3分の1の額を課税標準額とします。
宅地の税負担の調整措置
平成6年度に、評価の均衡化を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われ、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じるようになりました。
そのため、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした負担調整措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げ、あるいは据え置く一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
負担水準=前年度課税標準額/当該年度評価額(×住宅用地特例率(1月3日または1月6日))
負担調整措置(住宅用地の場合)
平成23年度まで
| 負担水準 | 課税標準額 |
| 1.0以上 | 当該年度評価額 |
| 0.8以上1.0未満 | 前年度課税標準額に据え置き |
| 0.8未満 |
前年度課税標準額+当該年度評価額×5%=(A) ただし、(A)が当該年度評価額×0.8を超える場合は、当該年度評価額×0.8 (A)が当該年度評価額×0.2未満の場合は、当該年度評価額×0.2 |
平成24年度・平成25年度
| 負担水準 | 課税標準額 |
| 1.0以上 | 当該年度評価額 |
| 0.9以上1.0未満 | 前年度課税標準額に据え置き |
| 0.9未満 |
前年度課税標準額+当該年度評価額×5%=(A) ただし、(A)が当該年度評価額×0.9を超える場合は、当該年度評価額×0.9 (A)が当該年度評価額×0.2未満の場合は、当該年度評価額×0.2 |
平成26年度以降(課税標準額を前年度と同額に据え置く措置が廃止されます)
| 負担水準 | 課税標準額 |
| 1.0以上 | 当該年度評価額 |
| 1.0未満 |
前年度課税標準額+当該年度評価額×5%=(A) ただし、(A)が当該年度評価額を超える場合は、当該年度評価額 (A)が当該年度評価額×0.2未満の場合は、当該年度評価額×0.2 |
令和3年度のみ
| 負担水準 | 課税標準額 |
| 1.0以上 | 当該年度評価額 |
| 1.0未満 | 前年度課税標準額に据え置き |
家屋に対する課税
評価の仕組み
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
|
再建築価格 |
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費。 |
|
経年減点補正率 |
家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗による減価を基礎として定められたもの。 |
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格には建築物価の変動割合が反映されます。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積要件・・・50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりませせん。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
一般の住宅新築後3年度分
長期優良住宅認定住宅新築の翌年から5年度分
耐震改修をした既存住宅に対する税の減額
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、令和6年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事(改修工事費が1戸当たり50万円超)を行い、改修後3ヶ月以内に耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体、建築士、指定確認検査機関等が発行)を添付して申告した場合に、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額(家屋)の2分の1を減額します。減額対象は、1戸当たり120平方メートル相当分までとなります。
(注意)住宅以外の建物については、不特定多数の者が利用する大規模建築物等について、平成26年4月1日から令和5年3月31日までの間に国の補助を受けて一定の耐震改修工事を行った場合に固定資産税が減額される制度があります。
バリアフリー改修をした既存住宅に対する税の減額
新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、65歳以上の者などが居住する住宅(賃貸住宅を除く)について、令和6年3月31日までに、廊下の拡幅や手すりの設置など一定のバリアフリー改修工事(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円を超え、改修後の住宅床面積が50平方メートル以上あるもの)を行い、改修後3ヶ月以内に工事明細書等を添付して申告した場合に、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額(家屋)の3分の1を減額します。減額対象は、1戸当たり100平方メートル相当分までとなります。
省エネ改修をした既存住宅に対する税の減額
平成26年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)について、令和6年3月31日までに、窓の断熱改修などの一定の省エネ改修工事(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円を超え、改修後の住宅床面積が50平方メートル以上あるもの)を行い、改修後3ヶ月以内に熱損失防止改修工事証明書等を添付して申告した場合に、改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税額(家屋)の3分の1を減額します。減額対象は、1戸当たり120平方メートル相当分までとなります。
償却資産に対する課税
会社や個人で事業をされている方が、その事業のために用いる構築物、機械・装置、車両、工具・器具及び備品等を償却資産といいます。
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産状況を1月31日までに申告していただく必要があります。
申告された資産について、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
| 前年中に取得された償却資産 | 評価額=取得価格×対応年数に応ずる減価残存率 |
| 前年前に取得された償却資産 | 評価額=前年度評価額×対応年数に応ずる減価残存率 |
(注意)上記により求めた額が取得価格の5%よりも小さい場合は、取得価格の5%が評価額となります
課税の対象となる償却資産
| 資産の種類 | 主な償却資産の例 |
| 構築物 | 舗装路面、門塀、外構工事、看板、煙突など |
| 機械及び装置 | クレーン等建設機械、印刷機械、ポンプなど |
| 船舶 | ボート、釣船、漁船、遊覧船など |
| 航空機 | 飛行機、ヘリコプターなど |
| 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車など |
| 工具・器具及び備品 | パソコン、陳列ケース、事務机、ルームエアコンなど |
課税の対象とならないもの
- 自動車税または軽自動車税の課税対象となる車両等
- 無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェアなど)
- 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
縦覧・閲覧制度
縦覧制度
納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを、縦覧帳簿に記載されている他人の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。
縦覧期間は、4月1日から第1期納期までの間で、所属の窓口でご覧になれます。手数料は無料です。
土地価格等縦覧帳簿には所在・地番・地目・地積・価格が、家屋価格等縦覧帳簿には所在・家屋番号・種類・構造・床面積・建築年・価格が記載されています。
閲覧制度
納税義務者等が自己の資産について、固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。
閲覧は年間を通して可能です。手数料は有料ですが、縦覧期間中に限り納税義務者が本人の資産を閲覧する場合は無料です。課税台帳の写しは10円で交付します
土地・建物の相続登記
土地・建物の所有者(納税者)が死亡した場合、固定資産は相続人の所有になりますので、相続による所有権移転登記を不動産の所有地を管轄する法務局で手続きを行ってください。
土地・建物の相続登記をする際には、戸籍謄抄本等が必要になります。相続登記についての詳しい内容については、最寄りの法務局にお尋ねになるか、以下の福岡法務局ホームページをご覧ください。
問い合わせ
- 福岡法務局ホームページ(外部サイトへリンク)
- 福岡法務局直方支局☎0949-22-1144
住宅用家屋証明の申請
住宅用家屋証明とは、個人が一定の要件を満たす住宅を新築または取得し、自己の居住の用に供することを証明するものです。
この証明を添付することにより、その住宅の所有権保存登記や移転登記などの際に係る登録免許税(国税)の税率の軽減を受けられます。
登録免許税の軽減率
| 登記の種類 | 根拠法 | 標準税率(軽減前) | 軽減後の税率 |
| 所有権保存登記 | 租税特別措置法第72条の2、74条、74条の2 | 1000分の4 | 1000分の1.5 |
| 所有権移転登記 | 租税特別措置法第73条 | 1000分の20 | 1000分の3 |
| 抵当権設定登記 | 租税特別措置法第75条 | 1000分の4 | 1000分の1 |
注:認定長期優良住宅の新築、または取得(新築のものに限る)にかかる登録免許税の税率は、さらに1000分の1まで軽減されます。
登記手続き・登録免許税の軽減について詳しくは、福岡法務局直方支局にお問い合わせください。
問い合わせ
福岡法務局直方支局☎0949-22-1144
申請方法
住宅用家屋証明申請書(住宅用家屋証明書も必要)に記入し、以下の条件や必要書類を添付して、所属窓口に提出してください。
受付時間
役場開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
適用条件
新築住宅
- 個人(自己)の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること)
- 新築または取得後1年以内の家屋の登記であること
- 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火建築物、準耐火建築物である、または国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
注:下記1、2の住宅に該当する場合、以下のとおり追加条件あります。
1建築後未使用の住宅‥‥取得原因が売買、または競落であること
2特定認定長期優良住宅(認定低炭素住宅)‥‥平成21年6月4日(平成24年12月4日)以降に新築された、または建築後使用されたことのない住宅であること
中古住宅
- 個人(自己)の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること)
- 新築または取得後1年以内の家屋の登記であること
- 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火建築物、準耐火建築物である、または国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
- 取得原因が売買、または競落であること
- 【令和4年3月31日以前に取得された住宅について】取得の日以前20年以内(鉄骨造、鉄筋コンクリート造等は25年以内)に建築された家屋であること
- 【令和4年4月1日以後に取得された住宅について】昭和57年1月1日以後に建築された住宅であること。(新耐震基準を満たした住宅であればこの限りではない)
注:耐震基準を満たす家屋との証明(耐震基準適合証明書等)があれば、築年数の要件が緩和されます。
注:特定の増改築、リフォーム等を行った場合、以下のとおり追加条件あり。取得時、新築された日から10年経過していること - 個人取得日以前2年以内に、宅地建物取引業者が取得した家屋であること。建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(上限300万円)以上であること
- 以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2(PDF:109KB)第2項第1号から第6号(別紙参照)までに定めるリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
- 50万円を超える、同項第4号から第7号のいずれかに該当する工事を行うこと
必要書類
| 新築されたもの | 新築後使用されたことのないもの | 新築後使用されたことのあるもの(中古) | |
| 住民票(注釈1) | 必要 | 必要 | 必要 |
| 確認済証及び検査済証 | 必要(注釈2) | 必要 (注釈2) |
不要 |
| 登記完了証 | |||
| 登記申請書の写し | |||
| 登記簿謄本 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 必要家屋未使用証明書 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 売買契約書・売渡証書等 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 認定申請書の副本及び認定通知書等 | 必要 (注釈3) |
必要 (注釈3) |
不要 |
| 耐震基準適合証明書 | 不要 | 不要 | 必要 (注釈4) |
| 住宅性能評価書の写し | |||
| 保険付保証明書 |
(注釈1)未入居の場合は、申立書(以下様式)及び現在の入居家屋の処分方法を確認できる書類等(賃貸契約書(最新のもの)、売買契約書、社宅(官舎)入居証明書等)が必要となります。
・申立書(PDF(70KB)/エクセル(60KB))
(注釈2)家屋の所在地、床面積、区分建物の耐火性能、建築年月日、取得年月日、構造の内容が分かるものであれば、いずれかで構いません。
(注釈3)認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合のみ必要となります。
(注釈4)買取再販売住宅取得の場合のみ。一定の耐震基準を満たしていることが証明される内容が分かるものであれば、いずれかで構いません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課局:税務保険課課税係
電話番号:0949-42-2115