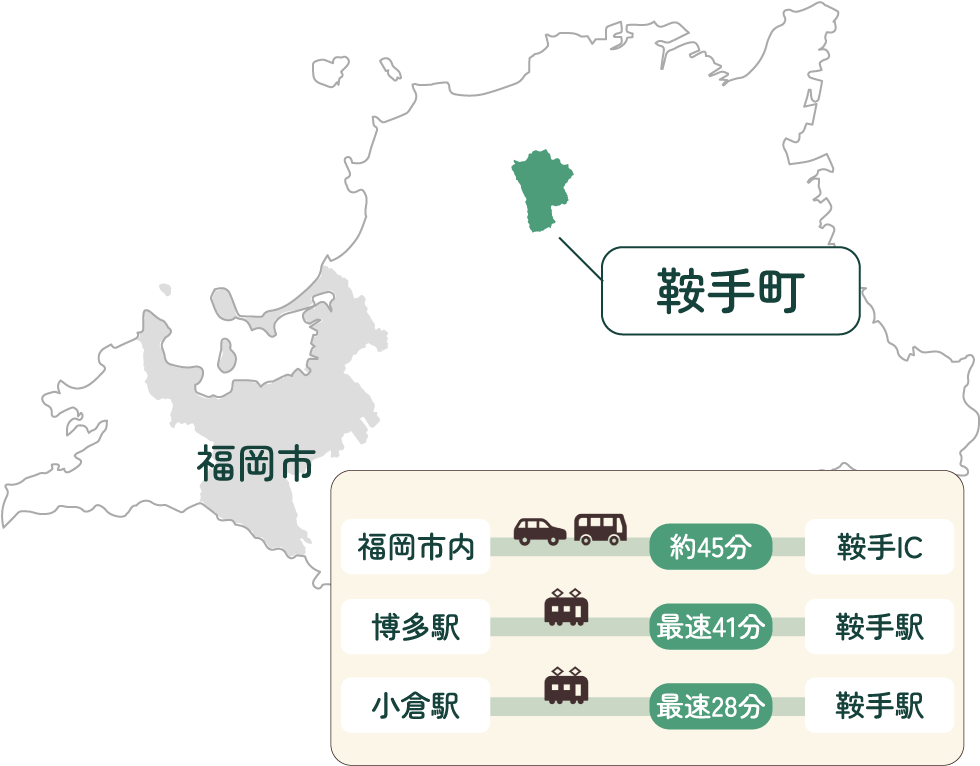保育所等について
ここから本文です。
保育所等を利用できる方
保育所等の利用を希望する場合は、教育・保育給付認定(保育認定)を受ける必要があります。
保育認定は、保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」に該当する場合に認定されます。
保育を必要とする事由
- 月48時間以上就労している
- 妊娠中、または出産から間がない
- 疾病もしくは負傷、精神や身体に障がいがある
- 同居、もしくは長期間入院等をしている親族を常時、介護または看護している
- 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっている
- 就労活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている
- 就学している(職業訓練校等における就業訓練を含む)
保育を利用できる「時間」と「期間」
保育を利用できる時間は、次の2区分です。
「保育標準時間」認定
フルタイム就労などが対象。施設や事業者の開所時間(延長保育開所時間を除く。)の範囲内で、1日最大11時間までの保育を利用できます。
「保育短時間」認定
パートタイム就労などが対象。各施設や事業者が設定する保育短時間の受入時間帯(8時間)の範囲内で、1日最大8時間までの保育を利用できます。
| 保育を必要とする事由 | 保育必要量(1日) | 有効期間 | |
|---|---|---|---|
| 8時間 | 11時間 | ||
| (1)就労 | 対象 | 対象 | 就労している期間 |
| (2)妊娠・出産 | 対象 | 対象 | 出産前2か月、出産後2か月 |
| (3)保護者の疾病・負傷・障がい | 対象 | 対象 | 診断書等により必要な期間 |
| (4)同居親族の常時介護・看護 | 対象 | 対象 | 介護または看護が必要な期間 |
| (5)災害復旧 | 対象 | 対象 | 必要な期間 |
| (6)求職活動 | 対象 | なし | 教育・保育認定日から3か月間 |
| (7)就学 | 対象 | 対象 | 就学している期間 |
| (8)育児休業取得中の継続保育利用 (注)育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて、継続利用することが必要と認められる場合に限る。 |
対象 | 対象 | 育児休業開始日から1年間 |
(注意)就労が理由の場合、保育標準時間認定は月120時間以上、保育短時間認定は月48時間以上の就労が必要です。
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の利用について
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の利用については、利用を希望する施設へお問い合わせください。
(注意)「保育を必要とする事由」に該当する必要はありません。
保育所等について
町内には、次の保育施設があります。
町立
| 区分 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 保育所 | 古月保育所 | 鞍手町大字木月111番地1 | 0949-42-0277 | 130 |
私立
| 区分 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 幼保連携型認定こども園 | 鞍手あゆみこども園(外部サイトへリンク) | 鞍手町大字中山2213番地2 | 0949-42-0300 | 130(注釈) |
| 幼保連携型認定こども園 | 鞍手のぞみこども園(外部サイトへリンク) | 鞍手町大字新延1986番地 | 0949-42-5911 | 80(注釈) |
(注釈)認定こども園の場合、保育認定の定員数
各保育施設の保育時間
通常保育
保育日
町立
日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く毎日
私立
日曜日、祝日及び年末年始(12月30日~1月4日)を除く毎日
時間
保育標準時間認定
午前7時~午後6時(最大11時間まで)
保育短時間認定
午前9時~午後5時(最大8時間まで)
延長保育
保育を利用できる時間帯を超えて保育を利用する場合は、延長保育の扱いとなります。
利用にあたっては、保育料とは別に利用料が必要となります。
| 延長時間 | 延長保育料 | 1か月上限額 |
|---|---|---|
| 午前7時から午前9時まで | 200円 | 2,500円(同月内の延長保育料が2,500円を超える場合) |
| 午後5時から午後6時まで | 100円 | |
| 午後6時から午後7時まで | 200円 |
(注意)私立保育施設の延長保育料については、各施設にお問い合わせください。
入所の申込み
次の申請期間内に、必要書類を提出してください。
| 保育の利用を希望する時期 | 申請期間 | 提出先 |
|---|---|---|
| 年度途中(5月以降)からの利用を希望する場合 |
利用を希望する月の前々月から前月10日まで |
役場所属 |
| 次年度4月からの利用を希望する場合 |
本年度12月1日から1月末日まで |
「継続入所児の弟妹児の入所」は各保育施設 「新規入所」は役場所属 |
(注意)原則各月の初日からの入所をお願いしています。
(注意)上記申請期間は、町内の保育施設の場合です。町外の施設への入所については、申込み期間が異なる場合があります。
必要書類
| 書類名 |
ダウンロード |
|
|---|---|---|
| (1)施設型給付費等支給認定申請書兼入所申込書 | ||
|
(2)保育を必要とする理由を証明する書類 (注意)保育を必要とする事由の()内の番号と同じ番号の書類を提出してください。 |
(1,8)就労証明書 |
(注意)(8)の場合は、就労証明書の育児休業期間欄の記載が必要です。 |
| (2,3,4,5)申立書 |
(注意)申立書に記載している添付書類が必要です。 |
|
| (6)誓約書 |
(注意)認定期間中、就職活動をしていることがわかる書類の提出を求める場合があります。 |
|
| (7)就学期間のわかる証明書等 | 指定の様式はありません。学校が発行する証明書等を提出してください。 | |
| (3)マイナンバー申出書 |
(注意)添付書類として、マイナンバーカードの写しまたはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類の写しが必要です。 |
|
| (4)鞍手町第3子以降保育料無償化確認書 (注意)申込をする0~2歳児の児童が、保護者が監護している生計同一のこども(年齢・同居別居問わず)の最年長者から数えて第3子以降に該当する場合、無償化の対象です。 |
||
| (5)転入に関する申立書 (注意)申請時点で鞍手町に住所がない方は提出してください。 |
||
支給認定通知書、入所承諾書の交付
提出された書類などで保護者の状況等を確認し、保育を必要とする状態にあると認定した場合は、支給認定通知書及び入所承諾書を交付します。
なお、定員超過等により保育施設での受入ができない場合は保留通知を発行します。
認定にあたっては、以下の事項を決定し、支給認定決定通知書に記載します。
区分
子どもの年齢に応じて、認定の区分を決定します。
【2号認定】保育を必要とする満3歳以上の子ども
【3号認定】保育を必要とする満3歳未満の子ども
(注意)新制度の幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用する満3歳以上の子どもは【1号認定】となります。
保育必要量
保育を必要とする事由及びその状況に応じて、保育を利用できる時間を決定します。
保育所利用者負担額
利用者負担額は、世帯の市町村民税の所得割額及び入所児童の年齢等によって決定します。4月から8月までは前年度の市町村民税額で、9月から翌年3月までは当年度の市町村民税額で算定するため、9月に保育料が変更になる場合があります。保育料が変更になった場合でも4月にさかのぼっての返還や追加徴収はありません。
令和7年度の保育所利用者負担額
令和7年度の保育所利用者負担額は次のPDFをご確認ください。
退所について
転出や家庭で保育ができるようになったときは、必ず事前に保育所に連絡し、退所届を提出してください。
給食について
給食は、幼児期に適した栄養価や材料を考慮し、おいしく食べられるように献立を工夫しています。
アレルギーのあるお子さんには除去食にて対応しています。
| 施設区分 | 主食費(ごはん代) | 副食費(おかず代) |
|---|---|---|
| 町立 | 1,000円 | 4,500円 |
| 私立 | 1,000円 | 5,000円 |
(注意)0~2歳児の給食費は、利用者負担額に含まれます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課局:健康こども課子育て支援係
電話番号:0949-42-2117