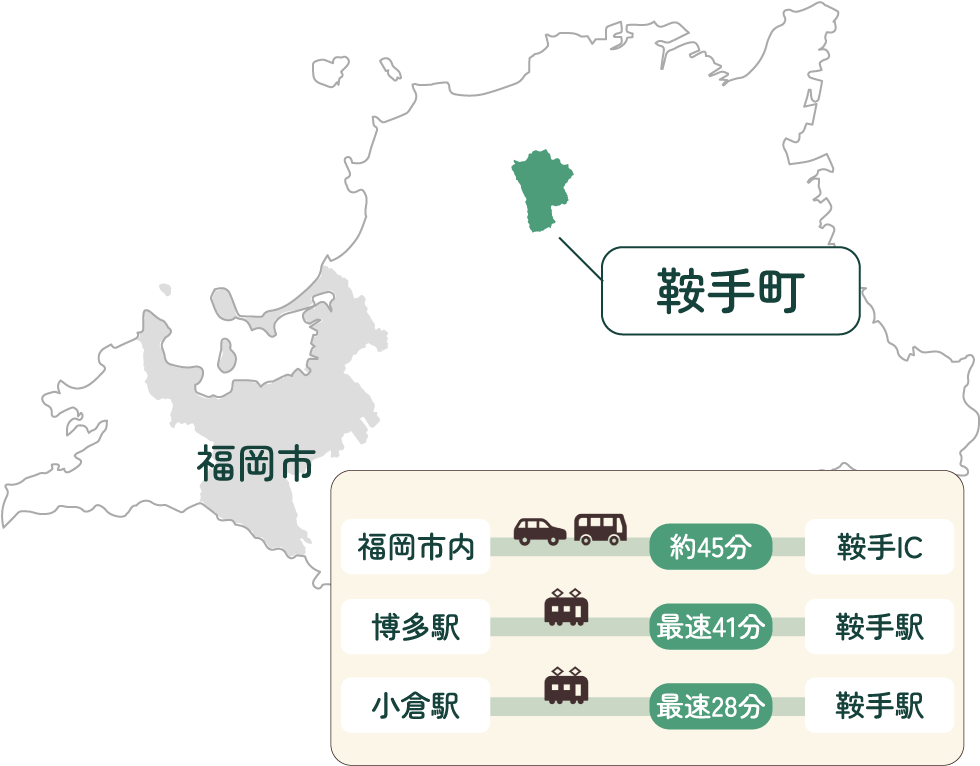国民健康保険について
ここから本文です。
国民健康保険は、病気やケガに備えて、加入者のみなさんがお金(国保税)を出し合い、必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。
職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人などを除くすべての人が加入します。
| 対象者 | 加入 | 喪失 | 給付 |
| 給付 | 高額療養費自己負担額 | 一部負担金の減免・徴収猶予 | 交通事故にあったとき |
| リフィル処方箋 | 各種様式 | 上手な医療のかかり方 | マイナンバーカードの健康保険証利用・初回登録の手順について |
| 医療機関等でのマイナ保険証での受診について | マイナポータルによる特定健康診査等に係る情報が閲覧できます |
対象者
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
加入
次の場合は、14日以内に届け出てください。
加入届が遅れた場合、その間の保険給付は行いませんが、保険税はさかのぼって課税されます。
- 転入したとき
- 職場の健康保険を喪失したとき
- 生活保護を受けなくなったとき
- 子どもが生まれたとき→出産育児一時金
届け出に必要なもの
- 健康保険資格喪失証明書(職場の健康保険を喪失した場合)
- 国民健康保険証(既に世帯の誰かが国保に加入している場合)
- パスポート、ビザ、外国人登録証(外国人の場合)
- ご本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
喪失
次の場合は、14日以内に届け出てください。
- 転出するとき
- 職場の健康保険に加入したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 死亡したとき→4.葬祭費ご確認ください。
届け出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 職場の健康保険証(職場の健康保険に加入した場合)
- 喪主の振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人)(死亡の場合)、葬祭費の領収証など
給付
国民健康保険に加入した場合は、次のような給付が受けられます。
1.療養の給付
病気やケガなどで診療を受けた場合は、自己負担以外を国民健康保険が負担します。
自己負担割合
| 70歳以上75歳未満 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 義務教育就学後 70歳未満 |
3割 | ||||
| 義務教育就学前 |
|
||||
2.療養費
緊急その他やむを得ない理由で保険証を提示しないで診療を受け、費用の全額を支払った場合、医師が必要と認めた治療用装具を購入した場合など、申請により基準の範囲内で払い戻しされます。
ただし、国民健康保険税の滞納が1年6か月を経過すると、給付の制限(全部または一部を差し止め)が行われる場合があります。また、差し止めされた保険給付額から滞納分の国民健康保険税が差し引かれる場合もあります。
届け出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 診療報酬領収明細書・領収書(緊急やむを得ない理由で保険証が提示できなかった場合)
- 装着証明書、見積書、請求書、領収書(治療用装具を作った場合)
- 世帯主の振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人)
3.高額療養費
1人が、同一月に同一の医療機関で治療を受け、支払った自己負担額が一定額を越えた場合、申請により所得階層に応じて払い戻しが受けられます。
ただし、国民健康保険税の滞納が1年6か月を経過すると、給付の制限(全部または一部を差し止め)が行われる場合があります。また、差し止めされた保険給付額から滞納分の国民健康保険税が差し引かれる場合もあります。
- 暦月ごと
- 病院ごと
- 総合病院は診療科ごと
- 入院と外来(通院)は別計算
- 保険が効かない差額ベッド代等は対象外
- 入院時の食事の自己負担額は対象外
70歳以上の方は、計算が異なります。
高額療養費自己負担額
1人が、同一月に同一の医療機関で治療を受け、支払った自己負担額が以下の表の金額を越えた場合、申請により所得階層に応じて払い戻しが受けられます。
詳しくは高額療養費をご覧ください。
70歳未満の人
| 所得(基礎控除後の総所得金額等)区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
|---|---|---|
| (ア)901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| (イ)600万円超901万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| (ウ)201万円超600万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| (エ)210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 57,600円 | 44,400円 |
| (オ)住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の人
| 世帯区分 | 一年以内に1~3回目 | 4回目以降 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
| 低所得 | Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | |
| Ⅱ | 24,600円 | |||
| 一般 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 | |
| 現役並み所得者 | Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
| Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
| Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | ||
- 低所得Ⅰとは、世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、かつ、各所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人をいいます(年金の所得は控除額を80万円として計算します)
- 低所得Ⅱとは、世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の人をいいます
- 現役並み所得者Ⅰとは、各種控除後の課税所得が年額145万円以上で、かつ年収が2人以上世帯で520万円以上の人、および同じ世帯の対象者をいいます(対象者1人の場合は年収が383万円以上)
- 現役並み所得者Ⅱとは、各種控除後の課税所得が年額380万円以上の人、および同じ世帯の対象者をいいます
- 現役並み所得者Ⅰとは、各種控除後の課税所得が年額690万円以上の人、および同じ世帯の対象者をいいます
届け出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 領収書
- 振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人)
- 印かん(世帯主本人が自署の場合は不要)
1.入院時の食事代
入院時には、1食460円の自己負担があります。ただし、次のように、住民税非課税の世帯は、申請により負担額が減額されます。また、1年以内に90日を越える長期入院の場合(連続でなくても可)、さらに負担額が減額されます。
- 非課税の場合
1食210円(70歳以上で低所得Iの方は、1食100円)
- 長期入院の場合(91日目以降)
1食160円
届け出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 請求書または領収書など入院日数がわかる書類(長期入院の場合)
2.限度額適用認定証(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)
入院する場合は「限度額認定証等」の申請手続きが必要になります。「限度額適用認定証」とは、各世帯の所得に応じた負担限度額区分が記載された認定証で、医療機関窓口での支払い負担を軽減することができます。
交付を受けるには、国民健康保険税に滞納がない世帯であることが条件となります。
届け出に必要なもの
- 国民健康保険証
3.出産育児一時金
被保険者が出産(分娩)したときに支払われます(妊娠85日以上の死産・流産を含む)。
- 令和5年4月から、支給額は原則50万円となっています。(産科医療保障制度に加入する病院などについて出産した場合に限られ、それ以外の場合は48万8千円となります。)
- かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みになっています(直接支払制度)。手続きについては、出産される予定の病院などにご確認ください。
4.葬祭費
死亡したときに、葬祭を行った方に申請により3万円が支払われます。
届け出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 喪主の振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人)
- 会葬礼状または、葬祭費の領収書(お亡くなりになった人、喪主の人の名前が正しく書いてあるもの)
5.高額医療・高額介護合算制度
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
世帯内の国民健康保険加入者の人全員が、8月から翌年7月までに支払った国民健康保険と介護保険の自己負担額を合計し(高額療養費などの支給決定額を除く)、算定基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します(国民健康保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象外です)。
合算した場合の限度額(年額・8月~翌年7月)
| 所得(基礎控除後の総所得金額等)区分 | 限度額 |
|---|---|
| (ア)901万円超 | 212万円 |
| (イ)600万円超901万円以下 | 141万円 |
| (ウ)210万円超600万円以下 | 67万円 |
| (エ)210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 60万円 |
| (オ)住民税非課税世帯 | 34万円 |
| 所得区分 | 限度額 |
|---|---|
| 現役並所得者 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者Ⅱ | 31万円 |
| 低所得者Ⅰ | 19万円 |
支給対象となる人には、役場より別途通知いたします。
一部負担金の減免・徴収猶予
国民健康保険の世帯主及び被保険者が災害、事業または業務の休廃止や失業等による収入の激減など特別な事情がある場合に、申請により一部負担金の支払いが困難と認められるときは、医療費の一部負担金が免除、徴収猶予されることがあります(最長6か月)。
なお、申請の決定には預金等の要件のほか、銀行や雇主等への調査を行います。くわしい条件や手続きについてはお問い合わせください。
交通事故等にあったとき
第三者行為による交通事故等でも届け出をすれば国保が使えます。その場合、医療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求します。
届け出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 事故証明書
- 第三者行為による傷病届(様式は役場にあります)
知っていますか?「リフィル処方箋」
リフィル処方箋とは?
症状が安定している患者について、医師が認めた場合、医療機関を受診することなく最大3回まで同じ薬を繰り返しもらうことができる処方箋です。
医療機関を受診する回数が少なくなり、通院の負担を軽減できるなど、患者にとってメリットがあるほか、結果として、医療の効率化も期待されています。
希望する場合は、まずかかりつけ医にご相談ください。
リフィル処方箋の使い方
1回目は、通常の処方箋と同様、処方された日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)の返却があります。2回目以降必要となるため、リフィル処方箋をなくさないようしっかり保管してください(コピー不可)。
2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。医療機関の受診がありませんので、服薬中に気になったことや症状の変化は薬剤師に相談してください。必要な場合は、医療機関の受診をお勧めします。
ご注意ください
- 投薬量に制限がある医薬品や湿布薬はリフィル処方箋の対象外です。
- リフィル処方箋を使用している期間でも、症状や体調に変化がある場合は医療機関で受診しましょう。
- 薬剤師が患者の服薬状況などを確認し、リフィル処方箋による調剤が不適切であると判断した場合は、調剤を行わず、医療機関への受診を勧奨する場合があります。
- 同一のリフィル処方箋は、同一の薬局で調剤してもらうことが推奨されています。
- 詳しいことは、かかりつけ医や薬局にお問い合わせください。
各種様式
- 高額療養費支給申請書(PDF:85KB)
- 療養費支給申請書(PDF:197KB)
- 被保険者証等送付先変更申請書(PDF:101KB)
- 国民健康保険異動届(PDF:97KB)
- 葬祭費支給申請書(PDF:46KB)
- 傷病届(PDF:195KB)
- 健康保険等資格取得喪失証明書(PDF:124KB)
- 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(PDF:100KB)
- 国民健康保険限度額適用等認定申請書(PDF:122KB)
- 国民健康保険委任状(PDF:46KB)
各種手続き等について、詳しくはお問い合わせください。
上手な医療のかかり方
必要な人が適切なタイミングで、安心して医療を受けるためには、一人ひとりの医療のかかり方が大切です。
上手に医療にかかることで、自分自身の金銭的、時間的、体力的な負担が軽減されるだけでなく、医療機関や医療従事者側の負担も軽くなります。
かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医は、これまでの病歴や健康状態、体質などを把握しています。病気やけがに関する相談ができ、必要なときには専門の病院を紹介してくれます。
かかりつけ薬局・お薬手帳を活用しましょう
必要以上に多くの薬を服用することで、薬が効きにくくなったり、有害な副作用が発生したりする状態を「ポリファーマシー」といいます。このポリファーマシーを防ぐために薬をしっかり管理し、必要以上の薬を服用しないことが大切です。
かかりつけ薬局を決めれば、処方薬や市販薬等の重複・飲み合わせの管理をしてくれるため、薬のムダがなくなります。また、副作用等の相談もできるので、薬を安全に服用することができます。
お薬手帳は、いつ、どこで、どんな薬を処方されたか記録しておく手帳です。手帳は1冊にまとめましょう。また、医療機関に受診する際には必ず持っていきましょう。
はしご受診(重複受診)は控えましょう
複数の病院を受診すると、医療費が余分にかかるだけではなく、検査やお薬でかえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。
ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効き目や安全性を持ち、費用が安くなる場合があります。自己負担だけではなく、医療費全体が安くなるかもしれません。医師や薬剤師にご相談ください。
夜間・休日の受診はよく考えてから
夜間や休日などの時間外に受診しようとする際は、平日の時間内に受診できないか、もう一度考えてみましょう。緊急医療機関は、緊急を要する重症な患者さんのためのものです。
救急安心センターを利用しましょう
急なケガや病気をしたとき、救急車を呼んだが方がいいか、今すぐに病院に行った方がいいかなど、判断に迷うことがあると思います。そんなとき、専門家からアドバイスを受けることができる電話相談窓口が救急安心センター事業(♯7119)です。
救急安心センター事業(♯7119)に寄せられた相談は、電話口で医師、看護師、相談員がお話を伺い、病気やケガの症状を把握して、救急車を呼んだ方がいいか、急いで病院を受診した方がいいか、受診できる医療機関はどこか等を案内します。
詳しくは、救急車の適時・適切な利用(総務省消防庁)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用・初回登録の手順について
マイナンバーカードの健康保険証利用の方法について紹介します。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには次の申請・登録が必要です。
詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
医療機関等でのマイナ保険証での受診について
医療機関を受診する際、健康保険証の代わりに、マイナ保険証で受診ができるようになりました。通常の健康保険証よりも、医療費を節約でき、自己負担も低くなります。
また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
詳しくは、マイナンバーカードが健康保険証等として利用できます(デジタル庁・総務省・厚生労働省)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
マイナポータルによる特定健康診査等に係る情報が閲覧できます
マイナンバーカードの健康保険証利用申込みをした方は、特定健康診査等に係る情報がマイナポータルで閲覧できるようになりました。また、医療機関や薬局でも、本人の同意を得たうえで特定健康診査等に係る情報が照会できるようになり、健康管理に役立てるようになりました。
詳しくは、マイナポータルで特定健診情報、後期高齢者健診情報を確認・取得する流れ(デジタル庁)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課局:税務保険課保険年金係
電話番号:0949-42-2115